#3
理論の何がうれしいのか
フィクショナルキャラクターの理論を例に
系共通科目(メディア文化学)講義A
月曜4限/第3回
松永伸司
2025.05.19
授業の進め方のおさらい [1/2]
授業資料について
-
PandAの「基本情報」にあるURLから、授業資料置き場(Scrapbox)に飛べます。そのページをブックマークしておくことをおすすめします。
-
授業資料置き場(Scrapbox)のURLは、オンラインで公開・共有しないでください。
-
授業資料は、基本的にスライド(いま見ているこれ)を毎回作る予定です。
-
紙で何かを配ることはありません。授業資料は、各自のノートPCやスマートフォンで閲覧してください。
-
スライドをPDFで見たい方は、Scrapboxの「スライドをPDFとしてダウンロードする方法」のページを見てください。
授業の進め方のおさらい [2/2]
Slidoについて
-
授業中に質問や感想などを投稿するツールとしてSlidoを使います。
-
SlidoのURLは毎回異なります。URLはScrapboxで共有します。
-
Slidoに投稿した内容は受講者全員に共有されます。
-
Slidoの投稿は成績評価には影響しません。
-
授業中いつでも書き込んでかまいません。
-
授業に関わる内容であればなんでもかまいません。
-
質問などに対しては必要なかぎりで反応します。
リアクションペーパーへの応答 [1/3]
リアクションペーパーへの応答
-
前回分のリアクションペーパーのコメントに対する応答は、Scrapbox上のページにまとめてあります。
-
取り上げているのは一部のコメントだけですが、実質的に授業内容の補足になっているので、発展的な勉強をしたい方は確認することをおすすめします。他の人が何を考えているのかもわかります。コメントを書くときの注意点なども記載することがあります。
-
基本的にQ&Aは毎回Scrapboxで書きますが、授業内でとくに紹介したいコメントはスライド(これ)上に記載することがあります。
リアクションペーパーへの応答 [2/3]
「Slido」の発音
-
公式の発音は「すらいどー」のはずです。「とめいとー」の「とー」と同じです。
-
公式のプロモーション動画の発音でも確認できますし、公式サイトでは発音についてわざわざ丁寧に補足しています。
-
とはいえ、日本では「すらいどぅー」読みが広まっていますね。なんででしょうね。
講義内で使われているSlidoですが、他の講義で使われている時担当の先生が「すらいどぅー」と読んでいました。松永先生は「すらいどー」(?)と読まれている気がするのですが、どれが正解なのでしょうか。
リアクションペーパーへの応答 [3/3]
抽象度の高い話題への関心
-
リアルな感想ですね。前にそういうことをちょっとツイートしたことがあります。
-
応答の続きはScrapboxで。
この世の人間(特に大学生)を、「抽象的な事象を考えることを心から楽しめる人間」と「身の回りの事象や具体に落とし込まれないと楽しめない人間」に分けた時、自分はつくづく後者であると感じた。
私は前者の人間を非常に羨ましく思う。この気質には生来の性格だけでなく、これまでに身につけてきた知識や経験も多大に影響しているだろうから、今からでも遅くないと信じて、自分も抽象的な思考を楽しめるための訓練を積んでいきたいと思った。
今日の授業のポイント
-
前回のやり残し①:「ちゃんとした」理論と「だめな」理論の基準についての考え方を理解する。
-
前回のやり残し②:理論にどんな有益さ(うれしさ)があるのかを大まかに理解する。
-
フィクショナルキャラクターについての既存の理論を例にして理論的研究とその有益さについての具体的なイメージを得る。
今日のメニュー
1. 理論の評価基準と理論のうれしさ
2. フィクショナルキャラクターの理論
1. 理論の評価基準と理論のうれしさ
-
前回授業のポイントのおさらい
-
日常で使われる素朴な理論
-
「学術的」な理論?
-
理論のうれしさ
前回授業のポイントのおさらい
大事なポイントだけ抜き出すと
-
この授業で扱う意味での「理論」とは、物事を理解・説明するためのフレームワークのこと。
-
その実態は、複数の概念が結びついた概念のネットワークである。
-
個々の概念の把握・伝達には、必ずしも定義(必要十分条件の提示)は必要ない。例示や特徴づけだけで、概念を十分把握できることがよくある。
日常で使われる素朴な理論 [1/3]
民間理論
-
この意味での理論は、「学問」の世界の中でだけ使われるものではない。わたしたちは、日々の生活の中で、多かれ少なかれ組織立った概念群を使って認識したりコミュニケーションしたりしている。
-
ただし、日常的な理論における概念の多くは、分節化が雑だったり(つまり、だいぶ性格が違う事柄をいっしょくたにまとめていたり、逆に同じような事柄をなぜか区別していたり)、不明確だったり(つまり概念の適用条件があやふやだったり)、組織化が不十分だったり(つまり概念間の関係がはっきりしていなかったり)する。
-
そのように日常で使われる素朴な理論・概念は、専門的な研究者が作るタイプの理論・概念と対比して「民間理論(folk theory)」「民間概念(folk concept)」と呼ばれることがある。
日常で使われる素朴な理論 [2/3]
民間理論と「学術的」な理論の対立
-
民間理論と専門的な理論が対立するケースがたまにある。
-
-
民間概念と生物学上の概念が食い違っているという状況のもとで、ある行為の法律上の扱いをどう考えればいいのかが問題になったケース。
-
経緯:
-
狩猟法によって、一定期間中にタヌキその他を捕獲することが禁じられた。
-
その期間中に、ある猟師がムジナを捕まえた。
-
生物学的には〈タヌキ〉=〈ムジナ〉だということで、猟師が逮捕された。
-
猟師は「うちの地方ではタヌキとムジナは別物である。私はタヌキは捕まえていない。ゆえに無罪である」と主張した。
-
一審・控訴審では有罪になったが、大審院判決で最終的に無罪になった。判決では、〈タヌキ〉=〈ムジナ〉という生物学上の分類は認めつつ、その同一視が十分に一般的な認識ではないとして猟師の故意責任が否定された。
-
-
日常で使われる素朴な理論 [3/3]
-
〈HSP〉という概念への批判
-
HSP(highly sensitive person)は、「感受性が高い人(それゆえにいろいろなしんどさがある人)」くらいの意味で使われている民間概念(もともとは心理学の論文で提唱された概念らしいが、曲解されて広まっているらしい)。
-
各種の発達障害やパーソナリティ障害などは精神医学上で認められた概念であり、DSM(精神障害の診断と統計マニュアル)に記載されているが、HSPは認められていない。
-
メンタルヘルスに関する民間概念は、人々の「正しい」自己理解・他者理解の妨げになり、ひいては治療の妨げになりえるという批判がある。
-
ただし、DSMに記載されているような精神障害も、概念による分類という点ではHSPと同じである点に注意。違いは(もしあるとすれば)その概念を使うことの有効さ・有益さ・体系性の程度といった点にある。
-
「学術的」な理論? [1/5]
民間理論と「学術的」な理論の違い
-
専門的な研究コミュニティで検討されることなしに流通している民間理論と、「学術的」「科学的」な理論は、どちらも概念のネットワークという点では違わない。だとすると、両者の違いはどこにあるのか。
-
民間理論はうさんくさい、「学術的」な理論はちゃんとしていて信頼に足る、みたいなイメージがあるかもしれない。しかし、そこで言う「学術的」とはどういうことなのか?
-
実際のところは、両者を区別するはっきりした基準はないし、違いも程度の問題である。とはいえ、ある理論が「ちゃんとしている」かどうかを判断するにあたって、いくつか気にするべき指標はある。
「学術的」な理論? [2/5]
「ちゃんとした」理論かどうかの指標
-
説明力:観測事実を無理なく説明できるどうか。
-
説明の一般性:個別のケースだけでなく、似たようなケースに広く当てはまるかどうか(有効性の範囲が広いかどうか)。
-
検証の度合い:専門家集団による批判的な吟味を経ているどうか。
-
体系性:他の諸理論との整合性があるかどうか。孤立しているほど概念ネットワークとしては脆弱になりがち。
-
厳密さ:概念が明確に定義されているかどうか(概念の適用条件がはっきりしているかどうか)。
-
方法の明確さ:決まった手順に沿ってやれば誰でも同じことができるかどうか(属人的でないかどうか)。
-
etc.
「学術的」な理論? [3/5]
注意点
-
これらの指標のうちのどれが重視されるかは、分野の性格やその都度の文脈(研究の目的など)によるので、一概にどれが一番大事とは言えない。「学術的」な理論は、これらをすべてを満たさなければならないということもない。
-
「学術的」であることの指標として「客観的」という言い方を持ち出したがる人は多いが、その語の内実をはっきりさせないかぎりは不毛な言葉なので、できるだけ使わないほうがよい。
-
実際、「客観性」という語はいろいろな意味で使われる(前頁の指標のいくつかが「客観性」と呼ばれる場合もあるだろう)。そのうちのどの意味での「客観性」が大事なのかを限定しないと意味がないし、どの意味での「客観性」であるのかを言えるのであれば、最初から「客観性」などと言わずにその意味をそのまま言えばいいだけである。
-
というわけで、「客観性」という語は使わないほうがよい。
-
ちくちくツイート集
「主観/客観」って言うなツイート
「学術的」な理論? [4/5]
想定される問い
-
「理論の評価基準はその都度の文脈によって変わる」と言うが、ではどういう文脈ならどういう基準で理論の良し悪しが評価されるのか?
「学術的」な理論? [5/5]
答え
-
結局のところ、理論の評価基準は、その理論(理解・説明のフレームワーク)を使って当の文脈で何がしたいのかという理論使用者の目的によって決まる(これは道具の評価について一般的に言えることである)。
-
何かと何かにきっちりした線引きをしたい(何らかの理由で)なら、当の概念が厳密に定義されていることが「よい理論」の基準になるだろう。
-
既存の理論との接続を重視する(何らかの理由で)なら、体系性があることが「よい理論」の基準になるだろう。
-
特別な能力がなくても理論を運用できることが重要(何らかの理由で)なら、理論適用の手順が明確であることが「よい理論」の基準になるだろう。
余談:理論のうれしさ [1/3]
理論的研究をしてどんないいことがあるのか
-
理論的研究は、日常的に使われる概念群(民間理論)よりも、何らかの意味でより役立つ概念群を提供することを目指していると考えるのがよい。
-
「何らかの意味でより役立つ」の内実は、おそらくいろいろある。
-
典型的な役立ち方は、説明や予測に役立つというものだろう。
-
哲学では、一見したところの謎(「パズル」や「パラドックス」と呼ばれる)を解消できるという役立ち方もよくある。
-
それ以外にも、思考の整理やクリエイティブな発想につながるという場合もあるだろうし、単純に知的好奇心を満たしてくれるという役立ち方もあるだろう。
-
余談:理論のうれしさ [2/3]
理論と解像度
-
一般的に言えることとして、専門的な理論を知ったほうが、日常的なものの見方よりも解像度がはるかに上がるという傾向はある。ようするに、物事をより細やかでクリアに見れるようになる。
-
もちろん、何かについての解像度が上がることを「役立つ」と感じるかどうか、そなることが「うれしい」かどうかは人によるだろうし、その対象への興味関心の度合いによっても大きく変わると思われる。
-
最終的には、文化の研究におけるいろいろな理論や概念にそれぞれどんなうれしさがあるのか(あるいはないのか)は、個々人で判断してもらうしかない。
余談:理論のうれしさ [3/3]
理論との付き合い方
-
理論(あるいはその構成要素である個々の概念)は、物事を見るためのひとつの道具、ひとつのメガネでしかない。それをまるまる信じて使うのも、自分のニーズに沿わない(あるいは単純に理解できない)という理由で否定するのも、理論が何であるかについて勘違いしている。
-
ちゃんとした研究分野内である程度認められている理論や概念は、それなりの検討と批判を経て生き残っている道具のはずなので、そのかぎりで尊重したほうがよいが、別に絶対的なものでもなんでもない。
-
自分のニーズにとって使えそうな道具なら吟味しながら使う、不十分に思えるなら少し改変する、使えなさそうならひとまず無視する、というのが、文化の研究をするうえでの無理のない理論との付き合い方である。
以下、理論的研究のうれしさを
実例から見ていきます
2. フィクショナルキャラクターの理論
-
フィクショナルキャラクターの例示と特徴づけ
-
高田の議論:キャラクターの外見をどう考えるか
-
松永の〈Pキャラクター/Dキャラクター〉
-
コスプレ論文での理論の応用
フィクショナルキャラクターの例示と特徴づけ [1/4]
理論的研究の具体例
-
文化についての理論的研究がどんなものか、またそのうれしさはどこにあるのかを具体的にイメージしてもらうために、フィクショナルキャラクター(以下煩雑なので「キャラクター」と省略)についての既存の理論的研究をいくつか紹介する。
-
以下で挙げる文献
-
高田敦史「図像的フィクショナルキャラクターの問題」(2015年)
-
松永伸司「キャラクタは重なり合う」(2016年)
-
岩下朋世『キャラがリアルになるとき』(2020年)
-
メディ文の卒論「コスプレイヤーはなにをどのように演じているのか」(2025年)
-
フィクショナルキャラクターの例示と特徴づけ [2/4]
『美学の事典』(丸善出版、2020年)
「キャラクター」の項から引用
※定義ではない点に注意!
特徴づけ+例示になっている。
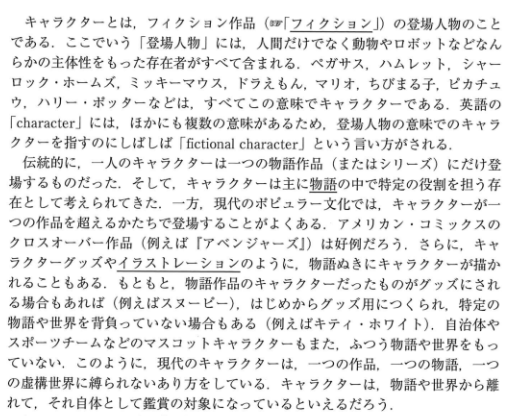
フィクショナルキャラクターの例示と特徴づけ [3/4]
キャラクター画像
-
この意味でのフィクショナルキャラクターを描く絵や映像を「キャラクター画像」と呼んでおく。公式・非公式の別はひとまず無視する。
-
キャラクター画像の例:
-
ドラえもんを描いているマンガの絵、ハリー・ポッターを描いている実写映像、ミッキーマウスを描いているアニメーションの映像、etc.
-
-
当たり前だが、キャラクター画像はキャラクターそのものではない。
フィクショナルキャラクターの例示と特徴づけ [4/4]
余談:「二次元」のキャラクター
-
俗語で「二次元キャラ」という言い回しがあるが、キャラクターは文字通りの意味では二次元(平面)なわけではない(ペラペラな存在として想像されているわけではない)。二次元なのはキャラクター画像である。この点で、キャラクターについての民間理論の言葉づかいにはすでに罠がある。
-
もちろん、その文脈で「二次元」という語で意味されているのは、おおむねキャラクターが特定の絵のスタイル(具体的にはアニメ絵)で描かれているというだけのことなので、いちいち真に受ける必要はないのだが、「二次元」という言葉づかいに引きずられてナンセンスな議論をする人々も少なからずいるので注意(2.5次元関係の文献はそんなのばっかりである)。
-
理論的研究はその手の罠を回避するのにも役立つ。
高田の議論:キャラクターの外見をどう考えるか [1/5]
文献の概要
-
書誌情報:
-
高田敦史「図像的フィクショナルキャラクターの問題」『Contemporary and Applied Philosophy』6号、2015年、https://doi.org/10.14989/226263
-
-
描写の哲学(=絵や写真についての哲学)をベースにして、フィクショナルキャラクターの画像に関する哲学的な問題を論じている。
高田の議論:キャラクターの外見をどう考えるか [2/5]
議論の前提
-
高田はまず、次の「キャラクター画像の非正確説」がもっともらしいことを示す。
-
キャラクター画像の非正確説:「公式の図像〔=キャラクター画像〕の一部は、キャラクターの形象的性質〔=見た目〕についてわずかにしか情報を与えない」という考え方。
-
非正確説によれば、マンガやアニメーションの絵や映像の多くはあくまでデフォルメであり、キャラクターの姿を正確に描いているわけではない。そこには誇張や歪曲がある。たとえば、キャラクター画像は、〈目が顔の大半を占める〉〈鼻が点である〉といった姿を描くことがあるが、それらの特徴は、当のキャラクターの正確な姿とは普通考えられない。
-
-
わかりやすい例:少女漫画の目が大きすぎるキャラクター
-
解釈が難しい微妙な例:クリリンの鼻問題
高田の議論:キャラクターの外見をどう考えるか [3/5]
パズルの提示
-
非正確説は正しいと思われるが、高田によれば、非正確説を受け入れると以下のパズル(一見解きづらい哲学的な難問)が導かれる。
-
キャラクターの美的性質のパズル:
-
①われわれは、キャラクターの姿が持つ美的性質を知っている(たとえば、〈かわいい〉〈かっこいい〉〈美しい〉など)。[観察される事実]
-
②われわれは、キャラクターの正確な姿を知らない。[非正確説からの帰結]
-
③あるものの美的性質を知るには、その形象的性質(=外見)を知っている必要がある。[美学の標準的な前提]
-
④上記の②と③を認めると、われわれは、キャラクターの姿が持つ美的性質を知らないことになる(というのもその正確な外見を知らないので)。
-
⑤しかし①と④は相反する(論理的に両立しない)。したがって、矛盾を解消するには、①②③のいずれかを否定しなければならない。
-
高田の議論:キャラクターの外見をどう考えるか [4/5]
パズルの解決
-
高田は、③(あるものの美的性質を知るには、その外見を知っている必要がある)を否定することでパズルを解決する。
-
高田の主張:
-
われわれは、たしかに物語上のキャラクターの正確な姿は知らないとしても、画像が直接描く〈分離された対象〉の正確な姿は知っている。なので、〈分離された対象〉の姿が持つ美的性質は、問題なく知ることができる。
-
マンガなどの画像を使ったフィクションの鑑賞では、一定の条件下で〈分離された対象の姿がしかじかの美的性質を持つならば、物語上のキャラクターの姿もまたその美的性質を持つ〉という取り決めが一般に成り立っている。
-
その取り決めのおかげで、われわれはキャラクターの姿を正確に知らなくとも、分離された対象の姿を知っているかぎりで、キャラクターが特定の美的性質を持つことを正しく知ることができるのである。
-
高田の議論:キャラクターの外見をどう考えるか [5/5]
高田における理論のうれしさ
-
哲学的なパズルの発見と定式化をする(哲学者はこれだけでうれしがれる)。
-
〈分離された対象〉という概念の導入、および〈ある種の画像を使ったフィクションには特殊な鑑賞規則がある〉という考えの導入によって、パズルを解決する。
-
パズルの解決そのものがうれしいというよりは、〈パズルを解決するためには、これこれのように考えなければ筋が通らない〉ということがはっきりするのがうれしい。
-
-
マンガやアニメーションなどのデフォルメ画像を使うフィクションの独特なあり方についての解像度が上がる。
松永の〈Pキャラクター/Dキャラクター〉 [1/6]
文献の概要
-
書誌情報:
-
松永伸司「キャラクタは重なり合う」『フィルカル』1巻2号、2016年
-
-
高田の議論(とくにその前提になっている非正確説)やその他の論者のキャラクターにまつわる諸論点を引き継ぎつつ、高田とはやや異なる観点から〈分離された対象/物語上のキャラクター〉におおよそ対応する概念を提示している。
松永の〈Pキャラクター/Dキャラクター〉 [2/6]
〈Dキャラクター/Pキャラクター〉の区別
-
Dキャラクター(diegetic character):
-
物語世界上の存在者(登場人物)としてのキャラクター。
-
-
Pキャラクター(performing character):
-
Dキャラクターを演じる演じ手(俳優)としてのキャラクター。
-
高田の〈分離された対象〉におおよそ対応。
-
-
松永によれば、マンガやアニメーションのような画像を使ったフィクションでは、キャラクターの絵・映像は直接的にはPキャラクターを描き、鑑賞者はそのPキャラクターの姿を通してDキャラクターの姿を想像する。
松永の〈Pキャラクター/Dキャラクター〉 [3/6]
俳優とのアナロジー
-
松永の議論では、PキャラクターとDキャラクターの関係は、実写映画(実写映像を使ったフィクション)における俳優とその人が演じる登場人物の関係に似たものとして想定されている。
-
実写映画における俳優と登場人物の関係:
-
われわれは、俳優の姿を通して登場人物の姿を想像する。
-
われわれは、俳優の姿は正確に知ることができるが、登場人物の正確な姿は知らない。
-
われわれは、俳優の姿については問題なく美的判断ができるが、登場人物の姿については少なくとも直接に美的判断ができない。
-
俳優は、登場人物を演じていないときにも(現実世界に)存在する。
-
われわれは、俳優が登場人物を演じているときでも、俳優についての言明と登場人物についての言明を区別できる。
-
松永の〈Pキャラクター/Dキャラクター〉 [4/6]
俳優とのアナロジー(続き)
-
マンガ・アニメにおけるPキャラクターとDキャラクターの関係:
-
われわれは、Pキャラクターの姿を通してDキャラクターの姿を想像する。
-
われわれは、Pキャラクターの姿は正確に知ることができるが、Dキャラクターの正確な姿は知らない。
-
われわれは、Pキャラクターの姿については問題なく美的判断ができるが、Dキャラクターの姿については少なくとも直接に美的判断ができない。
-
Pキャラクターは、Dキャラクターを演じていないときにも(「キャラクター空間」という物語世界とは別の独特な世界に)存在する。
-
われわれは、PキャラクターがDキャラクターを演じているときでも、Pキャラクターについての言明とDキャラクターについての言明を区別できる。
-
松永の〈Pキャラクター/Dキャラクター〉 [5/6]
松永における理論のうれしさ
-
高田の〈物語上のキャラクター/分離された対象〉をより明確で使いやすい概念に改定する。
-
高田のパズルをよりシンプルなかたちで解決する。
-
実写映画とマンガ・アニメーションのあいだに、ある程度類比的な構造があることがわかる。
-
先行するキャラクター論に接続できる(たとえば東浩紀のデータベース消費論)。
-
その他、キャラクターにまつわるいくつかの現象が説明できるようになり、キャラクターについての理解の解像度が上がる。
-
マンガという表現形式に特有の性格(それならではの特徴)の一部がはっきりする。
松永の〈Pキャラクター/Dキャラクター〉 [6/6]
この理論で説明できる具体的な事例
-
あるひとりのキャラクターのバリエーション(e.g. いろんなアリス)
-
かわいいけどかわいくないキャラクター(e.g. 『なにわ金融道』の「美人」キャラ)
-
姿の自然な/不自然な変化(e.g. 『地底国の怪人』におけるウサギのシームレスな変装解除)
-
既存のキャラクターからの新しいキャラクターの創造(e.g. スプー)
-
etc.
コスプレ論文での理論の応用 [1/5]
文献の概要
-
書誌情報:
-
著者名非開示「コスプレイヤーはなにをどのように演じているのか」京都大学文学部卒業論文、2025年
-
-
演技の定義論や高田・松永の理論などを援用しつつ、〈キャラクターを演じること〉という視点からコスプレイヤーの実践の独特さ(たとえば物語フィクションにおける俳優による演技とどう異なるのか)を明らかにしている。
コスプレ論文での理論の応用 [2/5]
議論の目的
第3章ではキャラクタ画像に着目して、コスプレイヤーがどのようなキャラクタの外見的特徴を表象しようと試みているのかについて分析する。コスプレイヤーの外見的特徴を大きく占めているのは、顔、体型、ウィッグであるため、本稿では特にメイクや加工、ウィッグ制作に焦点をあてる。
〔中略〕
Dキャラクタ、Pキャラクタという概念をコスプレの実践に導入し、コスプレにおける外見的特徴のキャラクタ表象を分析したい。コスプレにおいて外見の表象対象はDキャラクタであろうか、Pキャラクタであろうか。
コスプレ論文での理論の応用 [3/5]
理論的な区別を踏まえた上での著者の主張
さて、キャラクタの外見になるために、コスプレイヤーはキャラクタの資料を集め、設
定集を読み込むと先程述べた。また、Xでは、「#原作の隣に自分のコスを貼る」というハ
ッシュタグとともに、コスプレイヤーが原作のキャラクタのイラストの隣にコスプレを
した自分の姿を置いて、その再現性の高さをアピールすることがある。以上からも、コスプレイヤーがPキャラクタの外見的特徴を再現しようとしていることは明らかである。とはいえ、フィギュアや着ぐるみのようにPキャラクタを忠実に模倣するものではないだろう。
コスプレ論文での理論の応用 [4/5]
著者の主張(続き)
メイクや加工時の実践を2種類のキャラクタ概念を導入して説明してみると、以下のようになるだろう。
-
コスプレイヤーはPキャラクタの外見的特徴以外に、物語世界に存在するDキャラクタの外見的特徴にも注意を払ってメイクや加工、ウィッグ制作を行う。
つまり、コスプレイヤーはメイク等をする際に、Dキャラクタの鼻はこんな形だろうと解釈する過程を挟んでいるのだ。このような過程を踏まえメイクや加工を終えたとき、PキャラクタとDキャラクタが混ざった外見が完成するのである。
〔中略〕コスプレイヤーはキャラクタのアイデンティティとなる部分についてはPキャラクタを模倣していると言えよう。すなわち、その特徴がないと特定のキャラクタと分からない、という部分に関してはPキャラクタを再現する。
コスプレ論文での理論の応用 [5/5]
コスプレ論文における理論のうれしさ
-
コスプレイヤーたちが自身の姿かたちの制作において何をしているか、具体的には、何に価値をおき、何を目指して、どのような基準のもとに、メイクやウィッグ・衣装作りをしているかを、解像度が高いかたちで明確に記述できる。
-
コスプレ文化という実践の中にある多様性(コスプレ規範の多様性、SNS上でのさまざまな反応など)を説明できる。
-
他の種類の演技(俳優の演技など)とコスプレの類似点と相違点を明確に記述できる。
-
他の種類のキャラクター再現(ファンイラスト、フィギュア作り、メイクするのではなく顔の着ぐるみを作るタイプの着ぐるみコスプレ、etc.)とコスプレの類似点と相違点を明確に記述できる。
文献
今回引用した文献
-
高田敦史「図像的フィクショナルキャラクターの問題」『Contemporary and Applied Philosophy』6号、2015年 https://doi.org/10.14989/226263
-
著者名非開示「コスプレイヤーはなにをどのように演じているのか」京都大学文学部卒業論文、2025年
-
松永伸司「キャラクタは重なり合う」『フィルカル』1巻2号、2016年
-
松永伸司「キャラクター」『美学の事典』丸善出版、2020年
その他今回の話題に関連してとりあえず読んでおくとよい文献
-
東浩紀『動物化するポストモダン』講談社、2001年
-
伊藤剛『テヅカ・イズ・デッド』NTT出版、2005年
-
シノハラユウキ『物語の外の虚構へ』logical cypher books、2021年
描写の哲学・フィクションの哲学を勉強する用
-
清塚邦彦『絵画の哲学』勁草書房、2024年
-
清塚邦彦『フィクションの哲学』改訂版、勁草書房、2017年
リアクションペーパーについて [1/2]
-
毎回の授業後に、Googleフォームを通してその回の授業についてのコメントを提出していただきます。
-
GoogleフォームのURLは、授業後にPandAの「お知らせ」で共有します。
-
提出の締め切りは、その週の木曜日の23時です。
-
提出実績およびコメントの内容は、成績評価に使います(評価基準については次頁を参照)。
-
コメントは、名前を伏せたかたちで次回の授業で紹介することがあります。
-
重要そうな質問・疑問には、基本的にScrapboxのQ&Aページで答えを返します(すべてに返すわけではありません)。
リアクションペーパーについて [2/2]
-
コメントの内容は、その回の授業の内容(とくに重要なポイント)について、理解したこと・考えたことや疑問・質問などを自由に書いてください。高いクオリティはとくに求めません。重要なポイントがなんとなく理解できている(あるいはどの点が理解できなかったかを自分で理解している)のがこちらに伝われば、平常点の評価としては問題ありません。
-
ただし、以下の点に注意してください。
-
白紙やその回の授業に関係のないことしか書かれていない場合は、不提出と同じ扱いにします。また、ろくに授業を聞いてないっぽい(あるいはまるで理解してないっぽい)コメントの場合は大きく減点します。
-
日本語の文章として明瞭でない(何が言いたいのかぱっと読んでわからない)場合も減点します(非日本語ネイティブには配慮します)。
-
不必要な情報を書き連ねるとか、極端に冗長である場合も減点します。
-
スライドおわり
系共通科目(メディア文化学)#3
By Shinji Matsunaga
系共通科目(メディア文化学)#3
- 437



